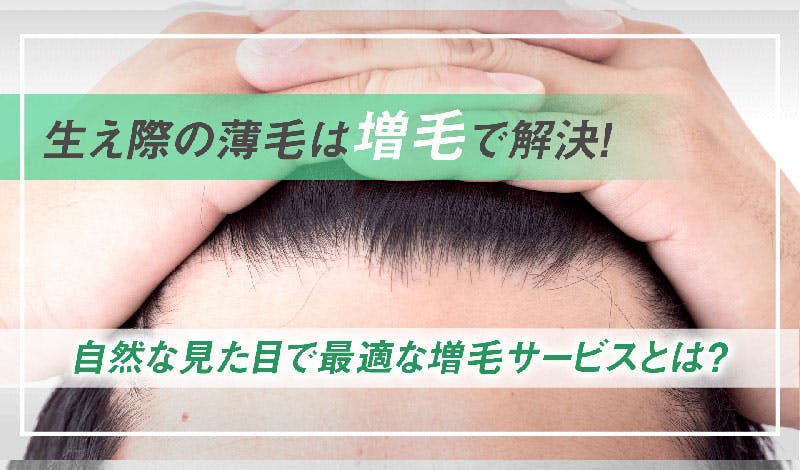【日体大/藤本珠輝】僕が、走り続ける理由 #1 ~全身脱毛症を公表、箱根駅伝へかける想い~
月刊誌、WEBサイトの編集を経てフリーランスとして活動。スポーツを中心に教育関連や企業PRなどの制作・運営に携わっています。屋外の取材が多く、髪の日焼けやパサつきが気になりつつも「髪コト」に参加するようになって、日々のケア方法などを実践するように。最近はヘッドスパにハマる中、みんなの人生を豊かにするよう記事づくりをしていけたらと思います。

真っ白なハチマキが、箱根路に揺れる。
20.8キロの道のりを駆け上がっても、駆け上がっても見える景色は灰色のまま。
「山登りだから、ずっとアスファルトだけが見えていて…」
そう話す言葉に、悔しさが滲む。
2020年1月2日。日本体育大学陸上競技部駅伝ブロック1年生の藤本珠輝は、第96回東京箱根間往復大学駅伝競走(箱根駅伝)の往路、最終5区を走るために小田原中継所のスタートラインに立っていた。たった一人、ジャンプをして足を伸ばす。手を胸に当てた表情が固い。その数秒後、歓声とともに笑顔で片手を上げる。
「哲さん!」
息を切らし、懸命に走り込んでくる太田哲朗に、大きく声をかけた。そして、しっかりと受け取ったタスキを握りしめる。
「駅伝は、想いが伝わる競技。タスキを受け取る時、渡す時に気持ちが伝わるんです。すごく必死な顔で走ってくる走者からタスキをもらって、受け取る走者は笑顔で応援しながら待っています。他の競技のことはわからないですけど、駅伝は気持ちが伝わる競技だし、それが魅力だと思います」
あの日、藤本が受け取ったタスキには、歴史と伝統。そして紡がれてきたみんなの想いが乗っていた。
「絶対、ゴールに届けないと」。その一心で、箱根の山へと駆け出した。
陸上はタイムがすべてじゃない

藤本が陸上と出会ったのは、中学1年生の頃だ。それまでは4つ上の兄とともにソフトボールをやっていたそうだが「野球部に入った兄がうまかったから、自分は絶対にやらない」と心に誓う中で、偶然、目にしたのが陸上競技だった。
「中1の部活動体験の時、長距離の選手が走っていたのを見ました。長距離なら、あまりお金もかからないし、自分の体一つで戦っていくのは面白い。見た瞬間に陸上部に入ることを決めました」
偶然は続く。
入学した兵庫県加古川市立陵南中学校は駅伝の強豪校。「そのことは知らなかった」そうだが、全国トップを競う選手たちの“走る姿”は、強く美しかったに違いない。
13歳になろうとしている彼が引き寄せられるように陸上と出会い、「幼い頃から長い距離を走るのは面白かったから」と長距離を選んだのは、少し大げさに言えば、運命にほかならない。
気づけば、力が一気に開花し、誰よりも速く走るようになっていた。そんな彼に、ある時、叱責が飛ぶ。

「中2の時、監督にめちゃくちゃ怒られました。『陸上はタイムで決着がつくけど、タイムがすべてじゃない。人間性も含めたものが陸上っていうスポーツなんだ。お前はもういらないから帰れ』って」
苦笑いを浮かべながら当時を振り返る。そして、言葉を続けた。
「怒られた時は『結果を出してるのに何で!?』って思ったんですよ。でも改めて考え直すと、長距離は個人種目だけど、駅伝になればチーム全体で戦っていくから、自分のことばっかりじゃダメだって。それに気づいてめちゃくちゃへこみました」
“走ること”と出会ってわずか1年。競技としての“走ること”の本質を学び、彼の成長はさらに加速していく。そこに待っていたのが、日本でも最も有名な駅伝の存在だった。
「中3で兵庫県代表に選ばれて、駅伝の都道府県大会(天皇盃 第21回全国都道府県対抗男子駅伝競走大会)に出場しました。中学生から大学生・社会人選手までがタスキをつなぐのですが、僕は西脇工業高校の加藤淳選手(現駒澤大学)からタスキを受け取って、西脇工高OBで駒澤大の中谷圭佑選手(当時)にタスキをつないだんです。
中谷さんは箱根駅伝に出場していて、区間賞も取っていました。そんな選手を間近で見て、箱根駅伝に出る選手はかっこいい、僕も走りたいと思ったんです」
そうして彼は、長距離の世界に導かれるように名門・西脇工高に進み、箱根を走るために関東の古豪・日体大へと歩みを進めることになるのだが、快進撃とも言える陸上人生の始まりは自分でも「ただただ、びっくりだった」と目を丸くするほど、あっという間の出来事だった。
それでも短い時間で、全国のトップに駆け上がった力は本物だ。
そのことを問うと困ったように眉をひそめて答えを探した。
「よく考えてみると、自分のことを振り返り、前向きに考えて修正することができる性格だったので、それが競技に合っていたのかな…。もちろん、反復練習も長時間走る練習も、あまり面白くないんですよ。でも、結果がでた時の喜びを思い浮かべたら、今やっていることがつながっていて、効果があることを理解できる。それがモチベーションですし、あの感覚を味わうためだったら苦しい練習もやろうって思えるんですよね」
だから走ることはやめられない−−。そう言っているかのようだった。
そしてもう一つ。彼が陸上に惹かれ、走り続ける理由を口にした。
「長距離を始めて、どんどん力がついてびっくりしましたけど、走れるもんだなって感じたんです。病気はあんまり関係ないなって」
藤本珠輝を襲った突然の全身脱毛症

藤本が、その症状に気づいたのは小学5年生の11月だった。
「小学校の昼休みに走り回って遊んでいて、汗ばんでいた頭をかいた手を見たら、髪の毛がびっしりついていて…」
今も忘れられないという、その光景に目を疑ったが、体調に変化はなく、当時は両親も自分も「すぐに治る」と思っていた。
「最初は頭の一部分だったのが、どんどんいろいろなところに広がって。抜け始めたら早かったですね。これはおかしいと思っていたら、病院で脱毛症と診断されました」
まだ10歳のころだ。彼の場合は、髪の毛も、眉毛もまつ毛も抜け落ちた。幼いからこそ、その姿を目にすれば「ショックだし、自分で自分を見ても気持ちが悪い」と、自己嫌悪に陥った。
追い打ちをかけるように、学校でも心を痛める言葉が飛び交った。髪の毛がないことを隠そうとニット帽で過ごせば、それもまた“からかい”の対象になる。
「どうしたって言われるんです」と、あの頃を思い出して視線を落とす。
「何で僕だけ…」
心は傷つき、行き場のない思いは、両親へと向かった。
「当たりましたよね、親に」
だが、そんな藤本を救ったのは、学校であり、両親だった。
「小6になる少し前でした。授業の終わりに、担任の先生が涙ながらに僕のことをみんなに話してくれたんです。それは嬉しかったですし、みんなの態度も一気に変わって。中学に上がる時には、みんなが気にしないのに自分だけが気にするのはおかしい」と思えるほどになっていた。
そして、心が少し軽くなった時、それまで見えなかったものも見えるようになっていた。
「隠れながらだったんですけど、両親が脱毛症のことをすごく調べてくれていたんです。僕のことを考えてくれていて、治療のために遠い病院に連れて行ってくれたり、たくさんのお金も自分たちの時間も使ったりしてくれていました。それなのに『何で僕だけ』と両親に当たるのは違うって思ったんです」
そんなふうに過去の自分を明るく話すが、まだ小学生。自分を律し、自らの病を受け入れるのは簡単ではなかっただろう。しかも藤本の場合は「抜けて生える、を繰り返す」のだ。
「だいたい1年半くらいの周期なんですけど、僕の症状は、全部抜けたと思ったら、また生え出すんです。小5で抜けたものが、中1の冬に生え揃って『完治した』って、すごく嬉しかった。でも中3の半ばくらいに再び全部抜けてしまって…その繰り返し。脱毛症は、一度治るともう発症しない人もいますし、逆にどれだけ治療をしても生えない人もいる。僕は、抜けて生えてを繰り返していて、特殊なんです」
10代の多感な時期に、髪の毛が抜けて生えてを繰り返す。精神的な痛みに加えて、治療もまた、長くつらい。頭皮に薬をつけて刺激を与えれば、頭はかぶれてかゆみが止まらない。液体窒素をひたした脱脂綿を当てたときには、やけどのような症状が出た。「とにかく痛い」ステロイド注射を何本も打って体調がくずれてしまったこともある。
それでも彼は、自らの病と、自分自身と向き合うことを止めなかった。

「陸上を通していろいろな支えができていました。走ることにひたすら打ち込んでいましたし、走ることで余計なことを考えることもなくなりました。とってもプラスに働いているんです。もちろん、競技をはじめてから頭を見られることは多々ありましたし、この症状でいる限り、言われるのは当然。だから気にするだけ無駄かなって受け入れたんです。気にし続けるくらいなら、陸上競技に打ち込んだほうがずっといいですから」
走り続ければ、当然人の目にさらされる。力をつければ、なおさらだ。
その結果、好奇の目で見られたり、心ない言葉が襲ってきたりしたとしても、走ることのほうが大きいですか?
そう問うと、はっきりと確かな答えが返ってきた。
「はい、大きいです」
そうして彼は、一つの結論にたどり着く。発症から7年。髪が抜けて3度目のことだった。「脱毛症のことはいろいろ調べました。この病気の人は日本にもたくさんいる。僕は両親にずっと支えられてきて、両親に感謝をするとともに、同じ病気で苦しんでいる人に『脱毛症でもがんばれることがある』ということを伝えたいと思うようになりました。それが走るモチベーションになっていたので、高3の終わりに公表することに決めたんです」
17歳になった彼が下した決断。それは、病気のことを隠さないことだった。
「病気はあんまり関係ない」
そんなふうに言い切れるほど、走ることは、何よりも強く藤本を支えている。そして「走ることをがんばれるのは、両親の存在があるから」とも、彼は言う。走り続ける原動力こそ、感謝の気持ち。そして、同じ症状で苦しむ人達へ、少しでも希望を届けたいという願い。
それがいつも、藤本珠輝というランナーの根底にある。
失意の箱根駅伝で見えたもの

2020年1月2日。日体大陸上競技部駅伝ブロックの藤本珠輝は、日本で最も有名な駅伝である『箱根駅伝』の5区を走るランナーとして、小田原中継所のスタートラインに立っていた。
山登りの5区は「チームの結果を左右する区間」。96回を数える箱根駅伝の歴史でも、多くのドラマが生まれてきた名所だ。そこに挑む1年生ランナーの姿には、多くの注目が集まった。同時に、彼が頭に巻いている“ハチマキ”にも。
「高3になってウイッグをつけて走るようになりました。最初はキャップをしていたんですけど、西脇工高の伝統であるハチマキが、ウイッグを固定するのにもちょうど良かったんです。大学生になってハチマキをつける人はいないんですけど、僕は、大学でもこれを続けようって決めたんですよね」
そうして彼は、トレードマークである“ハチマキ”姿で、箱根駅伝に挑んだ。
あこがれの夢舞台に立ち、ここで結果を出したい。そんな想いが頭をよぎる。
だが走りはじめて藤本は、箱根駅伝の本当のすごさを体感した。
スタートするまでは、緊張しなかったそうだが「走り始めたら沿道にあふれる人が目に入りました。箱根駅伝の影響力を走りだして、はじめて知ったんです。山を登っていても、どこでも多くの人がいた。冷静に走れたかというと」

そう言って、静かに首を振る。箱根の山は、描いていたような夢舞台でも、甘いものでも決してなかった。
1時間14分35秒。区間16位。初めての箱根で残した数字が、自分自身に重くのしかかる。
日体大もまた、総合17位に沈んだ。
悔しさを通り越して生まれた感情は、ただただ「申し訳ない」という気持ち。
走れなかった上級生たちの、引退をする先輩たちの顔が浮かぶ。
レース後、4年生から声をかけられた。
「お前一人のせいにはしない」
脱毛症で苦しむ人たちから励ましのメッセージも寄せられていた。
たくさんの人に向けた藤本の想いは、走ることを通して、きちんと届いていたのだ。
「自分のやってきたことは間違いじゃなかった。だからーー」
来シーズンはチームのために、みんなのために、もっと強くなって箱根を走りたい。
そう、強く想っている。
あの日、彼が受け取ったタスキには、たくさんの想いが乗っていた。
託された願い、つなぐ希望、紡いできた気持ち。
それを受け取ったから藤本は、未来に想いをつないでいく。自らが背負った責任と向き合い続ける使命を、そこに乗せて。
「駅伝は想いが伝わる競技なんです」
日本体育大学陸上競技部駅伝ブロック・藤本珠輝は、そうして今日も走り続ける。
【過去の取材記事はコチラから】
公開日:2020/08/26




 37
37